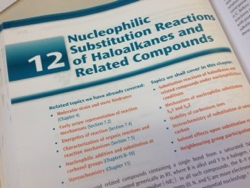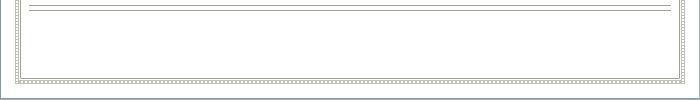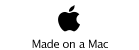いよいよ有機反応の中核をなす置換反応についての勉強です。今日はSN2反応。ハロアルカン(ハロゲンがついたアルカン)の求核剤による置換反応です。この反応はいくつかの事柄に分けて理解するとしやすくなります。
反応の形態や速度については、
速度:基質(ハロアルカン)と求核剤の両方の濃度に比例する2次反応
遷移状態:一段階反応であり、一つの遷移状態
立体化学:立体反転を伴う(ワルデン反転といいます)。従って、多くの場合RからスタートすればS体が得られます。
反応は脱離基の反対側から求核剤が攻撃して、5配位型の遷移状態を経て進行します。立体反転を伴うのはこのためです。後ろから攻撃していくのでその部分が立体的に混み合えば反応速度は遅くなります。たとえば臭化メチルのSN2反応の速度に対して臭化エチルでは0.08倍に遅くなり、臭化イソプロピルではさらに遅くなって0.014倍になります。分子模型をくむと求核剤が近づくべき方向がアルキル基を増やしていくとどんどん混み合っていくのがわかると思います。
反応は基質のみで決まるわけではありません。このほかに反応速度に影響を与える要因として、求核剤・脱離基・溶媒があります。
求核剤はより求核性の高い反応剤がより速く反応しますが、「求核性の高い」がくせ者です。求核剤とは炭素原子核を攻撃するもの、という意味です。求核剤の多くは「アニオン」になったものがありますが、これらは求核剤であると同時に、プロトンとも反応するので「塩基」です。ある場合は求核性と塩基性はパラレルな関係(求核性が高ければ塩基性も高い:酸素のアニオンの場合)にありますが、必ずしもこれは正しくなく、塩基性が弱いにもかかわらず、良い求核剤として作用することもたくさんあります。ハロゲンや酸素族の原子だと周期表の下の方にいけばいくほど求核性は高くなりますが、塩基性は逆に低くなります。
脱離基は求核剤に比べて簡単です。弱塩基になればなるほど良い求核剤となります。強塩基になる脱離基はよっぽどのことがないと抜けてくれない。求核置換反応では悪い脱離基に分類される脱離基は反応しないことになります。これはカルボニル化合物の付加脱離反応の章でも勉強したとおりです。
溶媒の効果は2つあります。一つは極性効果による安定化。もう一つは溶媒和、の効果です。極性効果は少々難しくて混乱しやすいのですが、簡単に考えると、原料系を安定化効果すれば、活性化エネルギーが結果的に大きくなって反応速度が低下し、逆に遷移状態を安定化すれば活性化エネルギーが小さくなるので反応速度は大きくなります。すなわち、原料のエネルギーのレベルを下げたら速度が下がるけれど、遷移状態のエネルギーのレベルを下げたら反応は速くなる。溶媒の極性による安定化が原料系と遷移状態のどちらで起こるか、あるいはどちらの効果がより大きいのかを考えるのが大事になります。
もう一つの溶媒和(溶媒による物質の取り囲み)は、どういう溶媒を使うかによって決まります。求核置換反応を考える場合は、求核剤に対する溶媒和は、プロトン性溶媒では溶媒との水素結合を主とした溶媒和が起こります。結果として求核剤は完全にプロトン性溶媒の取り囲まれてしまい、反応しにくくなって速度は低下します。一方非プロトン性極性溶媒(ジメチルホルムアミド・ジメチルスルホキシド・アセトニトリルなど)は、ローンペアを持つ溶媒では、カチオンの方を溶媒和するので(教科書の259ページのexample12.3を参照してください)、求核剤の方にはいかなくなって「裸の求核剤」を与えます。結果として求核置換反応は劇的に(場合によっては100倍以上)速くなります。
求核置換反応で悩ましいのは、求核剤は往々にしてイオンで水溶性、ハロアルカンは脂溶性、結果として両方がうまく混じり合わないことです。そんなときに活躍するのが「相間移動触媒(PTC)」。アンモニウム塩を使うことが多いですが、これは水と有機溶媒の両方に溶けるので、水ー有機溶媒の二相系の反応にすると、相間移動触媒が求核剤アニオンを有機相に連れて行ってくれて反応させ、脱離基となったアニオンを水相に連れ帰ってくれて、反応を促進します。