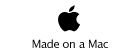有機化学1(2015)のページです。予習復習に役立ててください
有機化学1
さて、有機化学Ⅰの授業も最終章に入りました。ここまでよく頑張ってこれらたと思います。あと少しですね。
今日の内容はベンゼンの置換反応について勉強しました。芳香族化合物の特徴がよく現れた反応です。ベンゼン環はπ電子が6もありますから大変電子リッチです。このため求電子剤とは容易に反応できるはずです。同じような反応はアルケンへの求電子剤の反応でも見てきました。しかし、芳香属化合物には「共鳴安定化エネルギー」があります。この安定化はとても大きいので、芳香属化合物は「芳香族性を失いたくない」傾向があります。求電子剤がアルケンへの反応と同様にベンゼンに反応して行けば、ベンゼンのπ電子は4に減り、同時に求電子剤が付加した炭素はsp3混成軌道になりますから、芳香族性を失います。生じたカチオンはアリル系(正確にはペンタジエニル系)の共鳴安定化を受けなますから、かなり安定なカチオンですが、付加の際に芳香族性を失いますから、「芳香族共鳴安定化エネルギー」分の吸熱過程になるので、この活性化エネルギーはとても大きくなります。従って芳香属化合物はアルケンのように速やかには求電子剤とは反応できない。その結果、アルケンに臭素を作用させたら、即反応するのに、ベンゼンと臭素は混ぜただけでは反応せず、臭素の求電子性を強めるためにルイス酸を添加することで、活性化してはじめて反応が進行することが見られます。
さて、いったん付加した状態で、カルベニウムイオンが生じますが、アルケンの場合はこれにSN1的に求核剤が付加して反応が完結します。芳香族で同じように反応してしまうと、生成物は芳香族でなく脂肪族なので、最初のステップで失われた芳香族性が失われたままになり、結果として反応全体が「大きな吸熱」反応になってしまいます。これは平衡的にはとても不利です。一方、カルベニウムイオンのもう一つの反応であるE1反応してプロトンを失ってしまえば、π結合が復活し、ベンゼン環のπ電子も6に戻れるので、芳香族性を回復できます。こうなると失われた共鳴安定化を再び獲得でき、このプロトンを失う過程が大きな「発熱」反応になるばかりでなく、ベンゼンからスタートした反応全体も、少しの発熱反応になることができます。こうなると反応は進行しやすくなります。従って、芳香属化合物と求電子剤の反応は、求電子付加、E1反応で進行して、芳香族から芳香族を与える「置換反応」が主として進行します。アルケンへの求電子剤の反応が「付加」なのに対して、芳香属化合物への求電子剤の反応が「置換」となるのは、これが理由です。
求電子剤は、ハロゲン、ニトロ、スルホン酸、等があり、すべてルイス酸あるいは酸による活性化が必要です。炭素求電子剤で反応させる場合は、Friedel-Crafts反応があります。ハロゲン化アルキルもしくはハロゲン化アシルをルイス酸を加えて反応させて、ベンゼン環をアルキル化もしくはアシル化する反応です。アルキル化反応では、カルベニウムイオンを無理矢理発生させるので、その転位は避けられません、結果として直鎖アルキル基(第一級アルキル基)の導入はできません。一方アシル化反応では、アシリニウムイオンが活性中間体になるので、転位の問題は起こりません。ベンゼン環に直結したカルボニル基は容易に還元できるので、この方法は直鎖アルキル基を導入するには便利な方法になります。
さて、いくつかの置換基をベンゼン環に自由自在に入れるにはどうしたらいいでしょう。これは、今日勉強した反応の組み合わせが大事になります。でも、実行する順番も大事になります。これらのことは次週の授業で勉強します。

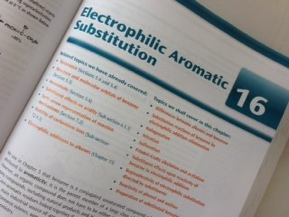
Tuesday, 14 July 2015
Electrophilic aromatic substitution, part 1