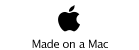有機化学1(2015)のページです。予習復習に役立ててください
有機化学1
アルコールの反応の1つめは酸性条件での反応です。アルコールを置換もしくは脱離させようとすると、最初に問題になるのがその脱離基としての「悪さ」です。仮にアルコールがそのまま切れて「水酸イオン」として抜けてしまえば、これは強塩基ですから、悪い脱離基となりますので、いま勉強している置換反応や脱離反能の脱離基としては作用できません。そこで、アルコールを「悪い脱離基」から「よい脱離基」にするためにどうするか?最初の戦略が「プロトン化」。酸性溶液中で反応させれば、プロトンはアルコールの酸素にプロトン化してOH2+になる。結果として脱離するものはOH-からOH2(=水)となって、「よい脱離基」になれます。こうすることで、これまで勉強した置換反応や脱離反能が可能になる。カルベニウムイオンが出やすい第二級や第三級アルコールなら、カルベニウムイオンを出して、E1やSN1反応をすることができます。硫酸中で炊けば脱水してアルケンができるのはこのプロセスです。脱離の方向は当然より安定なアルケンができる方向に進むので、ザイチェフ則に従った多置換アルケンが主として生成します。またヨウ化水素などを使えば、プロトン化したあと、ヨウ素イオンがよい求核剤なので、SN2反応してヨードアルカンが生じます。このようにプロトン化することで、水酸基は「よい脱離基」であるオキソニウムイオンに変換されて、いろんな反応ができるようになります。
ということは水酸基をよい脱離基に変えてやればいい。そのために変換するよい方法がトルエンスルホン酸エステルへの変換です。OH基をOTs基に変換することで、よい脱離基変換できるので、いろんな求核剤や塩基と反応して置換や脱理が可能となります。またこういう方法をとることで、プロトン化にはないメリットも生まれます。すなわちプロトン化をするためには酸性条件での反応条件が必須になりますが、塩基性の高い求核剤を使う反応では、この条件では求核剤(例えばアルコキシドアニオンなどが相当します)は速やかにプロトン化され(アルコキシドの場合はアルコールになってしまう)、弱い求核剤となるため反応は実行できません。しかし、トルエンスルホン酸エステルに変換しておけば、酸性だろうが、塩基性だろうが、中性だろうがあらゆる条件で反応できるので、アルコキシドも使って置換反応できます。アルコールをよい脱離基に変換しながら置換反応する試薬としてはほかに塩化チオニルや三臭化リンなどもあります。
さて、次に悩ましい話しは、カルベニウムイオンの転位です。これは難しい。有機化学の最難関といってもいいでしょう。詳しくは授業でお話ししたとおりですが、要約すると
1.カルベニウムイオンが発生すると、その炭素の最外殻電子は6となり、電子の入っていない空のpz軌道(空軌道)ができる
2.この空軌道に何とかして電子を入れて、少しでも最外殻電子を8に戻したい
3.超共役でちょっとだけ隣接炭素のC-HもしくはC-Cσ結合から電子を「借りてきて」埋めてちょっと安定化
というところまでは、前回お話ししたところですが、炭素はもう少ししたたかで
4.まてよ、いま借りてる超共役の2電子とその先についている水素(あるいは炭素)を、「完全移籍」させて、空のpzを埋めてカルベニウムイオンの状態を解消してもいいよな。そうすれば、自分のところは解決するし、となりにカチオンができてしまうけど、その位置は第三級カチオンだから、いまある場所が第二級カチオンだから、分子全体としてはもっと安定化が図れるし・・・
と考えるわけです。そして超共役で「部分レンタル」されていた電子を、「完全移籍」させてカチオンの炭素が代わる、そうしてより安定化されたカチオンができるなら、それでいい。骨格が代わってしまうのは何とも悩ましいですが、こうすることで、「より安定化されたカチオンに交換できる」のなら、分子にためらいはありません。さっさと転位して「安定なカチオン」にかわっていくわけです。転位では常に「ヒドリド(H+と2電子でH-)」あるいは、ヒドリドがない場合は「アルキルアニオン(Cと2電子)」は動いてカチオンであったpz軌道を埋めていき、抜けた先に新たなカルベニウムイオンを出します。そしてこれは、「より安定なカチオンがでる」場合に進行します。言い換えれば転位の結果「第二級カチオンが第三級カチオン」になるのなら進行しますが、「第三級カチオンが第二級カチオン」になるのであれば転位しません。転位の理解にはこの背景を認識しておくとわかりやすくなると思います。
最後にお話ししたのは、アルコールの酸化でした。アルコールはクロム酸などを使うと酸化されてカルボン酸やアルデヒド、ケトンになります。第一級アルコールの場合、クロム酸を硫酸酸性で使うとカルボン酸になりますが、酸性度を落として酸化力を弱めたPCC(ピリジニウムクロロクロメート)を使うとアルデヒドで酸化がとまります。第二級アルコールはいずれの酸化剤を使ってもケトンになり、第三級アルコールは通常は反応しません。これらの酸化剤とアルコールの反応は、有機に限らず化学におけるものづくりで使う方法論ですから、おぼえておいて損はありません。

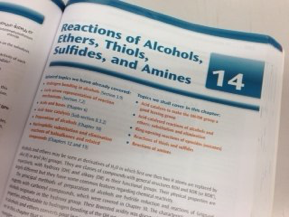
Thursday, 28 May 2015
Reactions of alcohols, ethers, thiols, sulfides, and amines, part 1