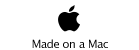有機化学1(2015)のページです。予習復習に役立ててください
有機化学1
さて、ハロアルカンの反応の最後を締めくくるのが脱離反応です。置換反応であるSN1、SN2反応と補完する関係にある反応ですから、一緒に関連づけて理解するようにしましょう。脱離と置換の違いは、ハロアルカンの「ハロゲンのついた炭素上でハロゲンが求核剤と置き換わる」のが置換反応、「ハロゲンのついた炭素とその隣接炭素からハロゲン化水素が抜けて炭素−炭素二重結合ができる」のが脱離反応です。求核剤もしくは塩基は、「ハロゲンのついた炭素を攻撃する」のが置換反応であり、そこへの攻撃が何らかの理由でできなくなったために、「ハロゲンのついた炭素の隣接炭素上の水素を攻撃して、脱ハロゲン化水素する」のが脱離反応である、ともいえます。また、E1とSN1反応は「ハロアルカンからハロゲンアニオンが抜けてカルベニウムイオンが発生して、そこからプロトンがとれる二段階反応」であり、E2とSN2は「反応性の高い求核剤もしくは塩基が直接炭素をバックサイドアタックしてワルデン反転して置換する、あるいはハロゲンのついた炭素の隣接炭素の水素を攻撃し、antiのコンホメーションを取りながらハロゲンアニオンとプロトンが同時にとれて脱離反応する」経路といえます。このためSN2とE2は「立体化学が規制された」一段階反応で進行することになります。
脱離反応の場合は、ハロゲンのついた炭素とその隣接炭素の間に二重結合を作りますから、「どっちの隣」に二重結合ができるのかが問題になります。脱離の仕方で、内部アルケンができる方向をザイチェフ則、1−アルケン(末端アルケン)ができる方向をホフマン則といいます。普通の脱離反応はザイチェフ則が主となります。一方立体的に混み合った塩基を使った場合では、内部の水素に塩基が届かないので、外からアクセスしやすい末端メチル基の水素を攻撃して1−アルケンができ、ホフマン則に従ったアルケンができてきます。
最後に、SN1、SN2、E1、E2の反応経路を比較しました。表にまとめられていますから、理解の助けにしましょう。第一級ハロアルカンでは、弱い求核剤では「反応しません」が塩基性の低い強い求核剤はSN2反応します。塩基性が高くてE2反応できる水素がある場合は脱離が優先します。第二級ハロアルカンでは、反応性の低い求核剤ではSN1、反応性の高い求核剤はSN2、塩基性が高ければE2となります。第三級ハロアルカンでは、求核剤が弱ければSN1、それ以外はE2が優先します。これらを整理して、ハロアルカンの「行く末」をしっかり把握できるように整理して理解しましょう。


Thursday, 21 May 2015
Elimination reactions of haloalkanes and related compounds