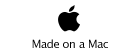有機化学1(2015)のページです。予習復習に役立ててください
有機化学1
有機分子には、異性体がつきものです。今日の勉強は光学異性体についてです。ひとことでいえば、「異性体同士が互いに鏡像の関係にあるもの」となります。異性体、ですから、そもそもが重なり合ってはいけません。違うものである、のが前提です。その上で、それら同士が「鏡に映ったものと同一になる」ところが光学異性体のポイントです。教科書にあるように、2−ブタノールやアラニンなどは光学異性体があります。高等学校の化学では「sp3炭素に4つの異なる置換基がついた場合に、光学異性体を生じる」と習いました。これはこれでほぼ正しいので、使い道はあります。が、そうでない場合も次の時間に出てくるので要注意です。
このような光学異性体を生じることを、キラリティを持つ、ともいいます。光学異性体のことはエネンチオマーといいます。また、光学異性体を持つようなもののことを不斉とかasymmetryとかいいます。これらは、2つ(光学異性体を2つ)並べると、対称に見える(そりゃ鏡像面が対称面になりますから)が、片一方では対称でない、という意味合いから来ています。実はキラルな(光学異性体を生じる)分子になるためには、「分子内に対称面を持たないもの」というのが条件です。sp3炭素に4つ異なる置換基がつけば(このような炭素のことを不斉炭素と呼びます)自動的に対称面はなくなりますので、光学異性体を生じ、不斉な分子になります。ですから、高校で習った考え方は「だいたいは」正しい。もし2つの置換基が同じものになれば、それで対称面ができてしまいますから、もはやキラルではなくなります。こういう分子(教科書の例では2−プロパノール)をアキラルといいます。
さて、このような不斉炭素上の立体化学の表記をどうしましょう。図で書けば簡単かもしれませんけれど、一言で言いたい。それはPrelog-Cahn-Ingold則による命名法です。命名法は2つのポイントからなり、1つめは官能基に順位をつける、2つめはその順位に従って立体化学を命名する、ことになります。 順位付けの詳細は教科書の39ページ(第2章)に載っています。 ルールは3つだけです。ルール1は「原子番号の大きいものが上位」だけです。もし原子番号が一緒なら「質量数で大きいのが上位」。ルール2は、それでも一緒なら、2つめの原子で同じルールで比較(原子番号、もしくは質量数)して決める。これで決まらなければ、ルール3、多重結合はそこに原子が結合していると仮想的に見なすのがちょっと面食らうかもしれませんが、これによってエチル、ビニル、アセチレニルの官能基の順位付けが、アセチレニル>ビニル>エチル>になります。
ここまで決めたらいよいよ立体化学の「つながり方」を決めます。第4位の置換基(多くの場合水素になると思います)を奥に持って行き、1位から3位の官能基の並び方が、右回り(時計回り)ならR、左回り(反時計回り)ならS、と命名します。いろんな表記法があるので、紙に書いてある化学構造を見て、決めるのが難しい場合があるかもしれませんが、常に4位を奥に見て決めるのを頭に置いておけば、書かれた構造式が「たまたま4位が手前」に来ていても、混乱せずにすみますね(詳しくはビデオの説明を見てくださいね)。模型をくめば簡単ですから、最初の間は、面倒がらずに模型をくんで学習してください。よくなれて、どんな分子でもR/Sの表記ができるようになっておきましょう。これはよく使います。天然型の光学活性なアミノ酸のほとんど(硫黄を含まないもの)の絶対立体配置が、Sであることもおぼえておくと何かと便利でしょう。

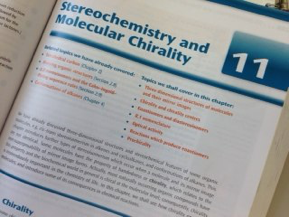
Tuesday, 28 April 2015
Stereochemistry and molecular chirality, part 1