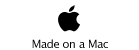有機化学1(2015)のページです。予習復習に役立ててください
有機化学1
カルボン酸誘導体の特徴的な反応である付加脱離反応は、正四面体中間体を経由します。この反応は前半の「求核付加」の段階と、後半の「脱離」の2つに分けて考えることができます。それぞれの反応の起こりやすさを決める要因を見ていきましょう。
「脱離」の段階では、脱離していくもの、一般に「脱離基(leaving groupもしくはnucleofugeといいます)」が脱離しやすいのがいい。脱離基が生成しても、それが生成しやすい、安定なものであればいいことになります。脱離基は一般に「アニオン」であることが多いですから、出しやすい「アニオン」は、結局は「弱塩基」になります。すなわち、よい脱離基=弱塩基、これは正しくいえそうです。実際、塩素イオンや酢酸イオン(酸塩化物や酸無水物からの反応の時の脱離基)は、出やすいので、これらは、今までに見てきた「付加脱離」反応はとても起こりやすいですが、一方でアルコキシドやアミドアニオンは、強塩基なので、出しにくく、結果として悪い脱離基として作用し、エステルやアミドからの「付加脱離反応」はそれほど速くなりません。
授業ではコメントしませんでしたが、この理屈だと中性のものが脱離基となるときには、それらはとてもよい脱離基になるので反応が早いことが期待できる。すなわち、水やアルコールが抜けていく反応はとても早い。そうなんです、酸性条件でのエステルの加水分解では、脱離基がアルコキシドではなくアルコール(プロトン化してから抜けてます)になるので、脱離野段階は充分早められるのです。言い換えれば、これが、「pull」の効果の本質でもあります。
次に、「求核付加」の段階の速度を決めている要因について考えましょう。
。カルボニルの反応性は、一言で言えば「カルボニル炭素上にどれほど+電荷がのってくれるか」で決まります。カルボニル基は共鳴構造でC+-O-になりますが、カルボニル炭素に隣接する脱離基Y上のローンペアが共鳴によってカルボニル炭素に電子対を供与してπ結合を形成する寄与が生じます。RC(O-)=Y+の寄与ですね。この寄与はカルボニル炭素上の+電荷の発生を弱めてしまいますから、この寄与が大きくなればなるほど反応性は下がります。電子の供与能力はN>O>ハロゲンですから、アミドが最も求核攻撃されにくく、酸塩化物が最も反応性が高くなります。
カルボン酸誘導体相互の反応は、ポテンシャルの高いものから低いものへの反応だけが進行します。ですから最もポテンシャルの高い酸塩化物を作ってから、エステルなりアミドなりに変換するのが定法です。
アミドやエステルを分子間で多数作ればポリエステルやポリアミドになり、高分子が形成されます。またアミド化やエステル化は、分子間反応よりも分子内反応が起こりやすい。天然にも重要な分子として分子内エステル(ラクトン)や分子内アミド(ラクタム)を持つ分子も多数存在しており、そういった分子をどのように合成していくか、というのも有機化学の大切な使命の一つです。
次回は第10章全部です.ページ数にして17ページありますから、早めに計画的に予習するようにしましょう。

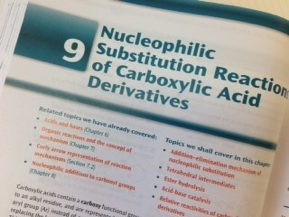
Thursday, 16 April 2015
Nucleophilic substitution reactions of carboxylic acid derivatives, part 2