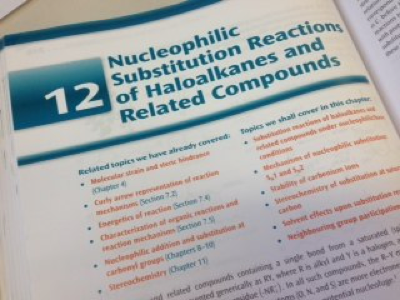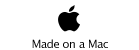Nucleophilic substitution reactions of haloalkanes and related compounds, part 2

求核置換反応の2回目はSN1反応です。前回の置換反応と反応生成物はにているものの、反応のメカニズムは全く異なります。SN2反応が一段階反応なのに対して、今回SN1反応は2段階(多段階)反応です。同じような基質からスタートして同じような生成物を与えるので混乱しそうですが、この違いは反応基質によって異なります。共役がない場合では、第一級ハロアルカンからはSN2反応が、第三級ハロアルカンからはSn1反応が進行し、第二級ハロアルカンの場合は主としてSN2時にSN1反応が進行します。SN1のポイントはカルベニウムイオン(カルボカチオン)です。この中間体のキャラクターがよくわかるとSN1反応が簡単に理解できます。しっかり勉強しておきましょう。
反応は、ハロアルカンからハロゲンがアニオンとして脱離してカルベニウムイオン中間体(カルボカチオン)が生じて進行します。このとき、脱離基はC-Y結合の2電子を持って行ってY-として出て行くために、炭素上の最外殻電子が8から6に減少します.このためカルベニウムイオンは安定な物質ではなく、反応の中間に一瞬少量だけ発生する「中間体」です。カルベニウムイオンになることで、中心の炭素はsp3混成軌道からsp2混成軌道になります。このため、出発のハロアルカンが光学活性であったとしても、カルベニウムイオンが発生したとたんにその立体化学についての情報(R/Sの立体配置)は失われてしまいます。SN1反応したあとの生成物がラセミ化するのはこれが理由です。
カルベニウムイオンは最外殻電子が6なので、「オクテット則を満たしていません。」そのため何とか電子数を8に戻したい、という振る舞いをします。最終的には求核剤のローンペアがカルベニウムイオンの空のpz軌道に「配位結合」して生成物を与え、めでたくカルベニウムイオンの状態を経験した炭素も最外殻電子が8に戻って解決するのですが(つまりはSN1反応が完了することになる)、その過程で、カルベニウムイオンは何とかして「分子のほかの部分から電子対をとってきて」8電子に近い状態になろうとして一時的な安定化を図ります。例えばカルベニウムイオン炭素の隣接位にアルキル基などが置換しておれば、隣接炭素のC-H(もしくはC-C)結合のσ結合の「2電子」が空のpz軌道に「なだれ込んで」、とりあえずはpzが「0電子」の状態を避けようとします。これを「超共役hyperconjugation」と呼びます。この安定化はそれほど大きくはないのですが、カルベニウムイオンが発生した直後の安定化には大きな役割を果たします。一般にカルベニウムイオンは第三級炭素>第二級炭素>>第一級・メチルの順に発生させやすくなりますが、これは超共役の安定化の可能性がたくさんある方が容易にカルベニウムイオンが出しやすいことと一致します。すなわち、超共役安定化がより効果的に働けば、カルベニウムイオンは出やすくなります。有機化学1の範囲では、第一級とメチルのカルベニウムイオンは絶対に出ない、と考えておいてかまいません(後述の共役による安定化のものをのぞきます)
超共役のほかにもカルベニウムイオンの安定化の効果はたくさんあります。大事なのは「空のpz軌道」をそのまま放置しない、ことであり、共役と接基関与などがあります。
共役ではカルベニウムイオンの隣接炭素に「π結合がある」もしくは「ローンペアがある」ことで、これらの電子対が空のpz軌道に電子供与してカルベニウムイオンを安定化します。これを共役による安定化(超共役ではありません)といいます。アリルカチオンやベンジルカチオンが発生しやすいのはこれが理由ですし、酸素に隣接した炭素のカチオンがでやすいのも、酸素のローンペアが空の軌道に電子供与してくれるからです。
空間的に電子対を供与することも可能で、これを隣接基関与(neighbouring group participation)といいます。教科書ではtrans-1,2-ハロシクロヘキサノールとその酢酸エステル誘導体の例が載っていました。これらの場合、ハロゲンが抜けてカルベニウムイオンが発生するときに、アルコールでは酸素のローンペアが空気道を埋めてエポキシド(酸素を含んだ3員環)になって安定化しますし、アセテートではカルボニル酸素が酸素を2つ含んだ5員環(ジオキソランといいます)を作ってやはり空軌道に電子供与して安定まします。このかたちを経由してSN2的に求核置換反応するため、trans体から出発してもtrans体を与えることになります。この場合はカルベニウムイオンに近いかたちをとって反応が進行しますが、SN1のようにラセミ化しないので注意が必要です。これは今後エポキシドの反応(教科書14章の300−301ページ)やアルケンへの付加反応(15章の322ページや325ページと326ページ)にも同じような考え方が出てきますので、関連づけて理解しておくといいと思います。
SN2反応とSN1反応は似たような生成物を与えますが、反応の経路は上記のように全く異なります。教科書にも表がありますので、違いを見分けられるようにしておきましょう。次回はハロアルカンのもう一つの反応経路である「脱離反応」を勉強します。
Tuesday, 29 May 2018