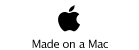Reactions of carbonyl compounds with hydride donors and organometallic reagents

この章ではカルボニル基へのヒドリドと有機金属試薬の付加反応について勉強しました。これまでの求核付加反応の旧核剤として、ヒドリドアニオンもしくはアルキルアニオンを求核剤として使った反応です。反応パターンは第8章と第9章で勉強したのがそのまま使えます(アミドの場合だけが少し悩ましいですが)
ヒドリドが付加すれば、還元反応です。ヒドリドは「水素アニオン」あるいは「プロトンに2電子持ったもの」をいいます。プロトンとは区別してください。これが求核的にケトンやアルデヒドカルボニル基に付加すると、アルコールに還元されます。還元剤はNaBH4がよく使われます。アルコール中ではこれはケトンとアルデヒドの還元には作用しますが、エステルは還元しません。エステルなどのアミド以外のカルボン酸誘導体を還元しようとすれば、NaBH4では無理で、LiAlH4を使う必要があります。これは強力な還元剤ですが、水とも発火を伴いながら反応するので、扱うときには注意が必要です。一般にエーテルなどの溶媒を用いて完全に非水条件(乾燥した溶媒を使う)で取り扱います。エステルの還元では、ヒドリドがカルボニル基に求核付加、次いでアルコキシドが脱離して、いったんアルデヒドが反応容器内で生成し、これがさらに還元されてアルコールまでいきます。ですから途中では止まりません。LiAlH4はケトンやアルデヒドも還元しますから、エステルとケトンの両方を分子ではLiAlH4では両方アルコールまで還元されます。
ヒドリドの反応のしやすさ(反応性)は、どういったものからヒドリドが出てきたかによって大きく依存します。一番シンプルな水素化ナトリウム(NaH)は、確かにヒドリドを出しますが、これは全く求核性(炭素に対する反応性)がなく、還元剤としては作用しません。一方BnBH4はそこそこの求核性を持ち穏和な還元剤としてケトンとアルデヒドのみを還元します。一方LiAlH4は強力な還元剤としてエステルもアミドもほぼすべてのカルボニル基を還元してしまいますし、水やアルコールなどのプロトンソースがあれば塩基として作用してたちどころに水素発生してしまうので、扱いにはとても注意が必要になります。このようにヒドリドと行ってもどういう物質から出てきたのかによって、化学反応性が大きく違いますので、全部同じだと考えないようにしましょう。
アミドの還元では、ヒドリドがアミドカルボニルに付加するところまでは同じですが、アミド基(NR2-)が脱離できない(悪い脱離基なのでC-N結合が切れていかない)ので、アルコキシドが抜けてイミンもしくはイミニウム中間体になります。これがさらにヒドリドノ攻撃を受けて、アミンへと還元されます。すなわち、アミドの還元はアミンを与えることになります。温度を下げて反応をすれば、正四面体中間体で反応はとまりますので、それに水を加えて加水分解すればケトンが得られることになります。(教科書に式がありましたね)
さて、カルボニル基を一気にメチレン基(CH2)まで還元するにはどうしましょうか。方法は3つあります。1つめはWolff-Kishner還元、2つめはClemmensen還元、3つめはジチオアセタールの脱硫です。Wolff-Kishner還元ではカルボニル基をヒドラジンを使ってヒドラゾンに変換し、これを強塩基と高温で強引に脱窒素させて還元する方法です。Clemmensen還元はベンジル位のカルボニル基(芳香環に直結したカルボニル基)の還元に限られますが、亜鉛アマルガムを使った穏和な還元法です。昔はよく使ったのですが、さすがに水銀を使いにくい世の中になったこともあり、最近は使われなくなりました。ジチオアセタールの脱硫ではカルボニル基をジチオアセタールに変換し、これをRaney Ni(ニッケルとアルミの合金の粉末をアルカリ処理してアルミニウムを溶かしだしたもの)を使うと脱硫反応してメチレン基になります。おそらくこれがこの目的では今一番よく使われている方法でしょう。Wolff-Kishner還元のメカニズムは授業ではややこしいので省略しましたが、一度自分で紙に書いて電子対の流れを追いかけて見るとよい勉強になります。
還元反応とアルデヒドからイミンに変換する反応(8章を参照してください)を組み合わせれば、アルデヒドやケトンをアミンに変換することもできます。このときは還元剤としてNaBH3CNです。これはNaBH4よりも反応しにくくてそのままではアルデヒドやケトンを還元しませんが、イミニウムイオン中間体は求電子性が高く、還元が起こります。これを還元アミノ化(reductive amination)反応といい、アミンを作る大切な反応です。最近ではNaBH3CNの代わりにNaBH(OAc)3を使うことが多くなりました。反応のパターンは全く同じです。
炭素−水素結合もヒドリド還元剤として使えるので、それを使った反応がCannizzaro反応とMeerwein-Ponndolf-Verley還元です。前者ではアルデヒドに強塩基条件で水酸基が付加したアルコキシドが、後者ではアルミニウムアルコキシドがヒドリド供与体として作用します。後者の反応ではアルミニウムイオンに対してイソプロポキシド(ヒドリド供与体)とケトンまたはアルデヒド(ヒドリド受容体で還元を受けるもの)が配位して、まるで一分子のように振る舞うことで、「分子内反応」となって反応が加速します。
グリニャール試薬に代表される有機金属試薬もカルボニル基に求核付加します。有機金属試薬は炭素と金属原子が直接結合した化合物のことで、C-M結合は電気陰性度の関係から炭素上がマイナスに分極する化合物です。従って、単純には「炭素アニオン」として求核剤として作用すると考えてかまいません。
Grignard試薬はハロアルカンとマグネシウムから発生できる試薬で、カルボニル基に求核付加(もしくは付加脱離)します。ケトンやアルデヒド相手には第三級もしくは第二級アルコールを与えます。エステルとの反応では2分子のGrignard試薬由来のアルキル基が求核付加して、第三級アルコールが得られます。これはヒドリド還元の時と同じパターンの反応ですね。アミドへの反応は途中で止まり、ケトンになります。これはどうしてなのかもう一度教科書を見てみましょう。
Grignard試薬の威力はすばらしく、非常に一般性の高い反応で、ほとんどすべてのカルボニル基に対して求核付加して炭素−炭素結合を作ります。この発見でGrignard先生はノーベル化学賞を受賞しています。簡単な分子から炭素数の多い分子を作るときにその威力を遺憾なく発揮します。どうやって目的の分子を作るのか、その戦略デザインが「有機合成」の考え方で、今回のGrignard試薬を使えばいろんなアルコールが合成できることがわかります。この考え方にも慣れていきましょう。有機分子を作りたいときには必要になります。
Grignard試薬の欠点は、反応しすぎること。カルボニルと見れば直ちに求核付加してしまいますから、反応させたい分子に複数のカルボニル基があったら、そのコントロールが問題になります。反応してほしくないカルボニル基をどうやって「キャップ」するか。それが保護基(protective group)の考え方です。クルマの塗装などで見るマスキングと同じような考え方ですね。教科書に載っている、アセト酢酸エチルエステルから、ケトンもしくはエステルあるいはその両方のカルボニル基を選択的に還元して対応するアルコールもしくはジオールをどうやって合成したらいいのかはよく復習しておきましょう。毎年試験に出しています(今年も出すとは限りませんが)
Tuesday, 15 May 2018