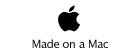化学Ⅱ
2018
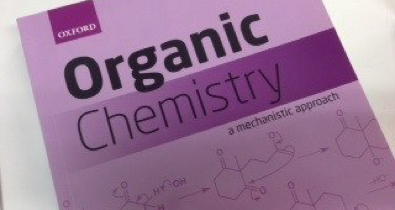
12月25日の中間試験の平均点は53点でした。87名の諸君が受験してくれました。最高点は96点でした。宿題と演習から出しましたから易しかったはずです。表面の正解率は62%であり、高校の延長であったこと、あるいは「ここは必ず出す」と言っていたところでしたので、比較的できていました。しかし、沸点と分子間力の関係、特に水素結合ではなく分散力が効いてくる問(ペンタンとネオペンタンの沸点鎖の説明)はできが悪かったですし、1,3-ジヒドロキシシクロヘキサンの安定コンホメーションの問題は、演習の時間の説明をちゃんと聞いていたかどうかがその明暗を分けました。
問題は裏面です。正答率は40%程度にとどまりました。芳香族の安定化のところも「必ず出す」と言っていたのでできはよかったですが、舟型シクロヘキサンのNewman投影はちゃんと舟型(ですから重なりコンホメーションになります)のNewman投影を教科書にあるように書けなかった人が多かったですし、シクロオクタテトラエンが折れ曲がった船の形を取る理由も、正確に「8π電子」なので「反芳香族」のため「共役しない」ために折れ曲がる、そのため単結合と二重結合の区別があるのだ、ということが書けていない人が多かったです。シクロヘキサジエニルカチオンの共鳴構造も教科書にありますからもう一度復習しておきましょう。
環歪みのエネルギー計算の問題は、教科書第4章の最後に計算方法をしめしてきっちり書いてあります。フタル酸の酸性度のところは第6章にあります(2カ所)。これらは化学のどの分野にいっても重要事項です。説明できるようにしておきましょう。
芳香族かどうかの判定も、演習でしっかりやりましたよね。分子模型をくんで「芳香族になれる」のか「なれないのか」示しましたよね。ちゃんと聞いていた(あるいはみていた)人は正解だったと思いますが、そうでない人が全部不正解になったのだと感じられます。自分で納得いくまで考え、その後に友人と相談(あるいは討論)して理解を深めて勉強を進めることが大事です。暗記ではとてもついて行けるレベルではありません。これは化学Ⅱに限らず「大学におけるすべての勉学」がそれに対応するものだと思います。これからは「頭を使って問題を考えて解く。正解に飛びつかない。正解に至るプロセスを考え抜く」そういった勉強を進めて下さい。そのための宿題であり演習なのですから。
期末試験は1月30日です。まだ少し時間はありますので、自分の頭を使って、考えてしっかり勉強するようにしてください。
中間テストの講評
10/01/2018