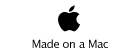化学Ⅱ
2017
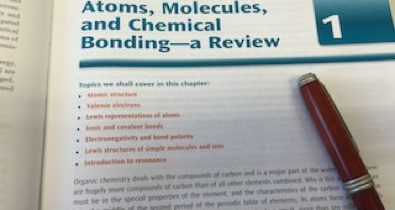
分子を構成しているのは、「原子」です。「原子」は物質の最小構成単位ですね。原子は「原子核」と「電子」から成り立っています。「原子核」は原子の性質を決める要素です。その質量は原子の大半を占めます。原子核には「陽子(proton)」と「中性子(neutron)」があり、それらの質量は「ほぼ」同じです。従って、原子の重さは「陽子」と「中性子」の和になり、これを「質量数(mass number)」といいます。陽子の数は原子番号(atomic number)ですから、その原子の「元素」を決定します。水素なら1、炭素なら6、酸素なら8です。一方中性子の数は、だいたいは陽子の数と同じくらいになることが多いですが、同じ元素でも異なる数を持つものがいくつかあり、それを「同位体(isotope)」といいます。同位体には安定なものもあれば、放射能を持つ不安定なものもあり、いろいろです。元素によっては1種類しかないものもありますが、だいたいの元素は安定同位体を2つ以上は持っています。例えば炭素は質量数は12のものと13のものがあり、その存在比が約99:1ですから、炭素の原子量(atomic weight)は、この両者の天然存在比を按分した値、12.011になります。原子量と質量数が微妙に違って、原子量が小数点以下何桁(最大で8桁)もあるのはこれが理由です。
電子も原子の重要な構成要素ですが、これは結合に大きくあずかるので、まずは原子の中でどのような振る舞いをしているのかを見ていきましょう。キーワードは周期律表の「周期(period)」と「族(group)」です。電子は-1の電荷を持ちますから、普通の状態の原子では陽子と同じ数あります。これらが原子核の回りを「回って」います。電子の存在する場所を軌道といいますが、これは量子力学的な方程式で規定されます。電子は「粒子」でもありますが同時に「波動」の性質を強く持ちますから、電子の軌道は「波動」方程式で記載でき、その解として出てくるのが原子における「電子」の軌道となります。わかりにくいかもしれませんが、電子くらいのサイズの世界では、我々の一般社会(サイズの物理学)の常識が通用しない、別のルールで支配されているのです。 軌道の種類はいくつかに分けられますが、エネルギーの最も低いものから1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, …となります。s軌道は球形対象の軌道、p軌道は3種類あり、それぞれx, y, z, 軸方向に広がった軌道です。電子はエネルギーの低い軌道から順番に入ってきます。1つの軌道には2つの電子が入れます(スピンは逆向き)。また2p軌道には、空いたところから電子が入ることになります(Hund則)。
こうして原子番号が増加するとともに、電子が入っていくことになりますが、1s軌道を満杯にしたHe、2s, 2pを満杯にしたNe、3s, 3pを満杯にしたArは、大変安定な原子になり、ほかの原子と電子のやりとりをしない原子になります。これが希ガスと呼ばれる元素で、電子はその状態がとても安定になり、単原子で存在する物質です。実は電子の配置が、これらの元素と同じ、すなわち2s,2p、あるいは3s, 3pが「満杯=8個の価電子(最外殻電子valence electron)」になると物質は安定となり、その状態になろうとするのですが、どうしたらいいでしょうか?それがこれから化学結合を考えるための大きなヒントになります。
電子の中でも価電子(=最外殻電子)が結合を考える際には大切になります。炭素だと4、ナトリウムだと1、塩素だと7です。これらは元素記号の回りに「・」を書いて表すことになりますが、これは次週の授業で詳しく説明します。価電子の数が8に近いもしくは0に近い場合だと、それらを失うか、補充するかで「8」にできますから、容易に安定になれます。こうしてナトリウムや塩素はそれぞれイオンになる傾向が高いわけです。1電子を失って陽イオン(=カチオン)になる時のエネルギーをイオン化エネルギー(ionization energy)といいます。アルカリ金属が最も小さく、族が大きくなるにつれて大きな値になります。イオン化エネルギーは中性の原子から、無理矢理1電子を引きはがすので、吸熱反応になります。吸熱なので、熱化学方程式の右辺の数値は「正の数」になります。電子親和力(electron affinity)は発熱過程になります(エネルギーは負です)。それに加えて、元素の電子を引きつけやすさの指標として電気陰性度(Electronegativity)があります。Paulingによって導入されたこの数値は、単位がなく、単に元素ごとの電子を引きつけやすさの「指標」として使います。有機化学を勉強するのでから基準は炭素で2.5であるのをおぼえておきましょう。周期表上で炭素よりも右側にある元素は電気陰性度は2.5よりも大きくなります。結合は主に2通りあります。一つはイオン結合(ionic bonding)。陽イオン(=カチオン)と陰イオン(=アニオン)がイオン的に(静電的に)結合する、という概念は大変簡単でわかりやすいのですが、有機化学では「100%イオン結合」という結合はありません。すべて共有結合の性質を持った結合であり、イオン結合は「部分的」でしかないのです。共有結合(covalent bonding)は文字通り「価電子を共有して結合」しているもので、これが有機分子の「化学結合」の中心的役割を果たします。例えば塩素は価電子が7ですが、2つの塩素原子がその1つづつを共有することですることで、お互いに価電子が8個になれるため、結合を作れるのです。共有結合は常に電子の「ペア(=2個)」であることに注意しましょう。
共有結合を作るには2個の電子がいるのですが、この2つの電子は結合している2つの元素に均等に配置しているとは限りません。結合している2つの原子が同じで対称な分子なら均等化もしれませんが、左右の元素が異なればそれらの性質が出て、一方に偏った配置になります。こうなると電子を引っ張った方の原子はやや負になりますし、引っ張られた(持って行かれた)方の原子はやや正になります。」これを分極(polarization)といいます。正確にはもっと多くの効果があるのでややこしくなるんですが、分極は結合を作っている2つの原子の電気陰性度の差で決まり、電気陰性度の大きな方がマイナスに電気陰性度の小さな原子の方がプラスに分極します。また分極すれば、その結合自体が正極と負極を持ったユニットとして見なせますので、それを双極子(dipole)と呼びます。双極子モーメントは有機化学の場合、δ+からδ−の方向に矢印を引きますが、それ以外の分野(無機化学など)では逆に矢印を引きますから注意してください。分子内に複数の双極子があれば、それらの「ベクトル和」が分子全体の双極子モーメント(dipole moment)となります。分極した炭素ー塩素結合を持つような分子でも、分子全体としては双極子モーメントが0になることだってあります(例えば四塩化炭素)。
Atoms, molecules, and chemical bonding – a review 1
05/10/2017