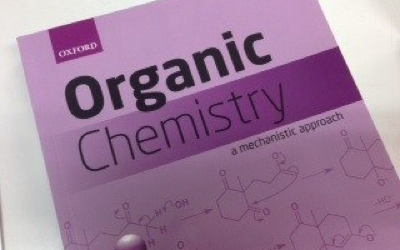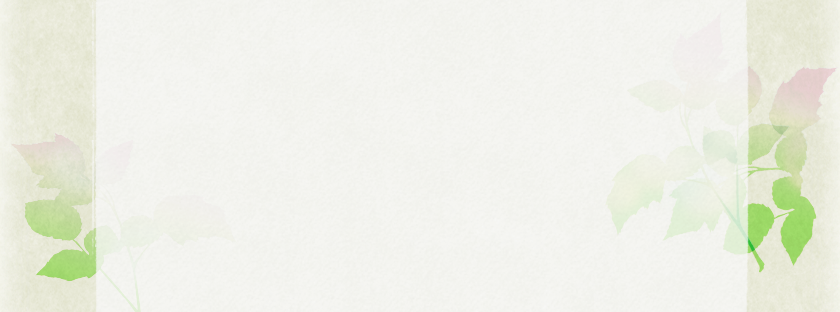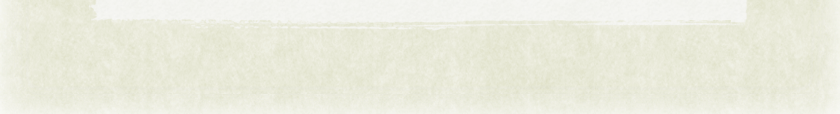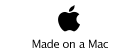平均点は62点でした。昨年度(65点)よりはやや下がりましたが誤差範囲です。良くできていたと思います。演習として実際に学習した問題や、中間試験で出た問題などは復習できている諸君が多かったのでしょう、比較的よくできていました。しかし、試験問題の最後の方にでたアミジンの塩基性の強さ(共役酸の共鳴構造)やマレイン酸の酸の強さ(水素結合)、あるいは、第8章に出てきた反応の問題(アセタールやWittig反応の生成物を答える問題)は正答率は低かったです。最後の所まで手が回らなかったのかもしれませんが、今後の有機化学の試験ではこのような反応を問う問題が多数出ますから、慣れておきましょう。春休みには有機化学Ⅰの範囲(16章まで)をしっかり読んでで予習しておくことを強くお勧めします。よい点を取った方の多くが予習をしてきていたのだと思いますので、これからも続けて勉強をする姿勢は続けていってください。
ところが、こと単位となるとそうは行かないのが残念なところです。結局合格率はこれまでと同じレベルになりました。試験の欠席を含めて約三分の一の諸君がもう一度の学習が必要な結果にせざるを得ませんでした。合格できなかった諸君の大半は、既出の問題は演習で一度はやった問題の答えさえも満足に書けないのですから、やむを得ません。いいわけは多々あるでしょうけれど、やっぱり絶対的な学習時間が足りないと考えられます。家に帰ってからいったい一日何時間勉強してますか?0に近くないですか?バイトで忙しいから、なんて言い訳してませんか?大学は勉強するところ。バイトなどのその他の活動は二の次、主たる活動の勉学がしっかりできてからの話しです。勉強する習慣をつけていただけなければ、今後も専門科目の単位を取れないでしょうから、当然の帰結として「卒業」はおぼつきません。すでに学生支援機構の奨学金が「留年をたった1回するだけで廃止」になる制度はスタートしています。世の中は厳しくなってきています。自分に不利なことがおこらないように、真摯な反省をした上で、自己の将来に向けた深い考察を今一度してみてはいかがですか。
4月からは有機化学Ⅰが始まります。範囲は第9章から16章です。今から毎日数ページずつでも予習をしておき、授業の始まる4月のはじめには、一度は全部の範囲を読み終えた状態にしておくこと。そして日々の学習について行けるようにしておいてください。まじめに予習をやった人はの将来は明るいと思いますが、その逆もきっと正しいのです。