化学Ⅱ(2014-2015)
いよいよ反応が出てきました。有機化学の勉強では反応が出てくると格段に難しくなると言います。しかし化学Ⅱの範囲では今日の分だけなので(簡単な酸塩基反応を除きます)、安心して反応の基礎的な事項を理解するようにしましょう。
カルボニル基への反応は有機化学の中心をなす反応です。それを最初に取り上げるのがこの教科書のユニークなところです。カルボニル基はC=O二重結合を持ちますが、共鳴構造によって炭素上は+になります。したがって、求核剤(ローンペアを」持つもの)が、カルボニルの空軌道(電子の入っていない軌道・LUMO・あるいは炭素のpz軌道)に「配位結合」して新しい結合ができ、反応します。今日取り上げた求核剤(ローンペアを持ち炭素と配位結合するこの)はCN-、H2O
などを勉強しました。CNが反応するとシアノヒドリンが得られます。これは平衡反応なので、その平衡位置はカルボニル化合物の種類に依存します。一般にアルデヒド(カルボニルの片側もしくは両方が水素)の場合は反応しやすく、平衡はシアノヒドリンに傾きますが、ケトン(カルボニルの両方の置換基が水素でなくてアルキル基やアリール基)の場合は、平衡は原系(すなわちケトン側)に傾きます。これは立体的な要素が効いており、カルボニルの状態ならsp2混成軌道なので2つのアルキル基は120度の角度で離れていられますが、シアノヒドリンになってしまうと、sp3混成軌道となるために角度が109度に狭められます。そのためより混み合うので、この状態をきらい、結果として平衡は原系に傾きます。
またシアノヒドリン化や水の付加はカルボニル基の活性化(たとえば隣接位に電子求引性基をつける)などすることで反応は速くなります。たとえばアセトアルデヒドよりもクロロアセトアルデヒドの方が、カルボニル基の分極(カルボニル炭素の+性)が大きくなるので、求核攻撃(ローンペアは電子なので−性をもつ)を受けやすくなり、シアノヒドリン化や水の付加が起こりやすくなります。
有機反応の場合は一般に塩基触媒(アルカリ条件)で反応が早くなる場合は、逆の酸性条件でも反応が加速される場合が多くあります。これは求核付加を例にとれば、電子のドナー(求核剤・ローンペア)の反応性を塩基性条件で高くしてやっても、電子のアクセプター(求電子剤・カルボニル炭素)の反応性を酸性条件で高くしても反応は速くなることを意味します。したがって、有機反応をうまくコントロールするには2つの反応基質のどちらを活性化するか、そこにかかっているのです。この考え方は今後もよく出てきますので頭に入れいておきましょう。
カルボニル基へはいろいろな求核剤が求核付加します。その中で酸素求核剤、たとえば水やアルコール、および窒素求核剤、第一級アミンや第二級アミン、は付加した後「脱水」するのが特徴です。最初にカルボニル基への求核付加を制御する要因についておさらいしました。2つの効果、すなわち立体効果と電子的効果は反応(あるいは平衡)をコントロールします。立体効果は、単に置換基のサイズが「どれほど邪魔になっているか」を示しているものなので、邪魔になる置換基(サイズの大きな置換基)があればあるほど平衡は不利になります。一方で電子的効果は、共鳴安定化すればするほど、原料が安定化されてしまうので平衡は不利になります。ちょうど、立体効果では生成物の安定度が失われ、エネルギー的に高くなるのですが、電子的効果では共鳴安定化されれば原料のエネルギーレベルが下がって、平衡が不利になる、ともいえます。
カルボニル基への水の付加はgem-ジオールを作りますが、これは一般には不利な生成物であり、ホルムアルデヒドなどの例外を除いてはカルボニル化合物のほうが主として存在することになります。一方がアルコキシドであるヘミアセタールは、分子内で生成する場合を除いては安定ではありません。しかし、分子内ヘミアセタールで代表的な化合物がグルコースなどの糖のピラノース構造ですから、重要な化合物であるのには代わりありません。
アルデヒドをアルコール中酸触媒と作用させると、アセタールができます。これは、途中まではヘミアセタールができる反応と同じですが、その後脱水(プロトンがシフトしていることに注意してください)して、活性化されたカルボニル中間体になります。この中間体は、カルボニル酸素にプロトンが配位結合しているのではなく、炭素−酸素結合がくっついているので、切れません.アルコール中での反応ですから、大過剰の存在しているアルコールが求核付加して、アルコール由来のプロトンが抜けてアセタールができます。このように、アルコールの付加では脱水を伴いつつ2分子のアルコールが付加していく反応が起こります。求核付加は同じですが、脱水プロセスが新しい反応として出てきました。これもしっかり把握しておきましょう。
アミンとの反応は第一級アミンと第二級アミンで最終生成物が異なります。しかし、途中のイミニウム中間体の生成までは全く共通ですから、あまり悩まなくていいかもしれません。アミンは求核性が高いのでそのままでもカルボニル基に求核付加し、生じたアルコキシドアニオンとアンモニウムカチオンをプロトンがシフトすることで、中和します。次いで反応系が弱酸性(pH=4程度が最適)なので、ヘミアミナールの水酸基にプロトン化が起こり、水が抜けてイミニウム中間体が生じます。第一級アミンの場合はイミン窒素上に残ったプロトンが外れることでイミンになりますし、第二級アミンの場合はカルボニルの隣接炭素上の水素がプロトンとして外れることでエナミンとなります。
Wittig反応はカルボニル基を一段階でメチレン基に変換する反応です。反応はイリドと呼ばれる活性種がカルボニル炭素を攻撃して進みます。イリドRCH=PPh3は対応するホスホニウム塩と塩基から発生します。カルボニル酸素がとれて見かけ上脱水が進行するのはリンと酸素の親和性のためと考えられています。
このように、求核付加もいくつかのパターンに分けられることがわかりました。付加するだけ、付加脱離、付加して脱水、いずれも最初のステップは同じで、後に同置換基が寄与するか(抜けるか、プロトンがシフトするかなど)で決まります。よく整理して理解するようにしましょう。
2月3日はいよいよ最終試験を行います。これまで勉強したところの基礎的な問題を出すことにしていますから、しっかり勉強してください。教科書を読むだけではダメですから、必ず紙と鉛筆を多用して「自分で書いて」あるいは問題を「自分で答案を作って」勉強するようにしてください。模型をくむのも有効です。しっかりがんばってください。
カルボニル基への求核付加反応です。反応のパターンは全部同じなので、把握しておきましょう
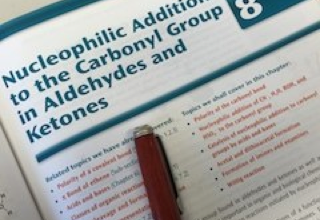
Tuesday, 27 January 2015....
Nucleophilic addition to the carbonyl group in aldehydes and ketones





