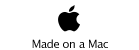化学Ⅱ(2014-2015)
いよいよ有機反応について勉強するところまで来ました。第7章は有機反応の考え方、そのポイントについてまとめた章です。取り立てて有機反応を学習してきたわけではないので、今のところは理解しにくいところもあるとは思いますが、これからの学習の基礎となるところなので、これからも新しい反応が出てくるたびに繰り返し参考にして把握するようにしていきましょう。
さて有機反応が起こるとは、何が起こるのでしょうか。反応が起こるからには、分子の変換が起こります。もっと具体的に見ていくと、そこには化学結合の「組み替え」が起こります。すなわち、有機反応が起きるためには、
共有結合の切断と形成がおこる
ことが必須になります。つまり有機反応とは
共有結合にあずかっている電子対が、移動して新しい共有結合なり非共有電子対になる
現象とも言えます。ですから、「共有結合にあずかっている電子対」がどのように動くのか、を明らかにすれば有機反応が理解できることになります。
共有結合(σでもπでも)はふつう「電子対」であり、2つの電子からなります。例えばA-Bという共有結合を持つ分子があって、原子Aと原子Bの間の共有結合が切れるためには、この2電子を、Aに2電子、Bに0電子と分配されて結合が切れるか、AとBそれぞれに1電子ずつ分配されて結合が切れるか、そのいずれかになります。前者を「ヘテロリシス」といい、後者を「ホモリシス」といいます。これから勉強する有機反応のほとんどは前者の「ヘテロリシス」を経由する「イオン反応」なので、このような結合の開裂が主に進行します。後者のホモリシスはラジカル反応で見られる結合切断様式であり、これは教科書の20章で詳しく勉強します(言い換えればそれ以外の章で出てくる反応はほとんどが前者のイオン反応ということになります)。
さて、結合が切れることはこれでわかりました。共有結合ができるときは、この逆のことが起こればよいのですから、
一方の原子が2電子を供給し、もう一方の原子がその電子対を受け取って共有結合になる
と考えたらいいわけです。従って電子を与える側は
非共有電子対、もしくはπ結合(たまにσ結合)
を与えればよく、電子対を受け取る側(0電子の側)は
空軌道(電子の入っていない軌道)
をもっておればよいことになります。そして結合の形成は、
非共有電子対(もしくはπ電子対)が、空軌道と相互作用する、「配位結合」の形式
で進行することになります。これが有機反応における共有結合の形成の基本パターンです。
では、空軌道を持つ原子についての注意事項はどうでしょうか。ここで前に勉強した「オクテット則」を思い出しましょう。炭素をはじめとする第二周期元素は「最外殻電子の数が8」が最大であり、9電子や10電子というような最外殻電子数を持つことはできません。これは第3周期元素でもほぼ同じように考えて差し支えありません(例外は硫酸とリン酸の硫黄とリンです)。すなわち、オクテット則を満たさねばならないかぎり、有機化学で扱う原子は(水素をのぞきます)、4つの軌道しか持ち得ない。もし共有結合がすでに4つある、あるいはローンペアの数と共有結合の数を足して4つある、場合には、その原子の最外殻軌道はすべて使われており、空軌道はありません。ですからアンモニウムNH4+の場合は、窒素はすでに4つの水素と共有結合していますから、「空軌道はない」ことになります。一見+の電荷を持ちますから電子がないように見えて、空軌道がありそうな錯覚に陥るかもしれませんが、実はないのです。ですから、アンモニウムは「配位結合をこれ以上作れない」ことになって、ローンペアを持つ分子を持ってきても窒素上には結合はできないことになります。一方ボラン(BH3)のBは結合が3つしかないので(しかもローンペアはない)、1つの「空軌道」をもち、ローンペアやπ電子対と「配位結合形成」をとおして新しい共有結合ができることになります。
次に、共有結合形成はどうして起こるのか。一言で言えば結合を作った方が「トータルのエネルギーを下げることができる」らに他なりません。一般にこのような配位結合形式で共有結合ができる場合、電子対を与える軌道(非共有電子対もしくはπ軌道)と空軌道が相互作用して、エネルギーの低い軌道と高い軌道ができます。電子対は新しくできたエネルギーの低い軌道に入ることで、結合形成前よりも形成後の方が低いエネルギーに持って行けるため、結合を作った方が得、となって共有結合ができることになります。
残りは反応の形式と言葉です。
有機反応には置換・付加・脱離・転位の4つの反応形式があります。また協奏反応といって、2つ以上の電子対の移動が一気に起こる反応がよく起こります。協奏反応では、2つ以上の電子対の流れが一度に起こるので、オクテット則を超えるように見える電子対の流れが起こりえますが、これも一つ一つの流れが段階的ではなく、一気に起こってしまうので、オクテット則を超えることはない電子の流れになる訳です。このような電子の流れは「巻き矢印」で示します。これになれてもらうことがこれからの有機化学の勉強になる訳ですが、今のところ最も大事なことを最後にまとめておきましょう。
矢印は、「電子対のあるところから、これから行く先(新たな結合あるいは非共有電子対)に向かって」引く。矢印に向きが逆にならないように気をつけましょう。
有機反応の考え方について総括して見ていきました。概念ごとの意味するところを整理しておきましょう
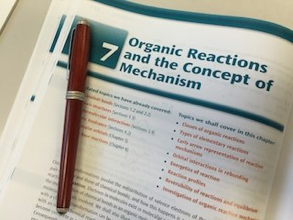
Tuesday, 13 January 2015....
Organic Reactions and the concept of mechanism 1