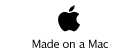化学Ⅱ(2014-2015)
有機化学だけではなくて他の分野の化学の理解にも酸と塩基の概念は大変役に立ちます。今日はブレンステッドの酸塩基の体にとその使い方について勉強しました。
ブレンステッドの酸塩基の定義は「プロトンH+」を基準に考えます。すなわち、プロトンH+供与体(出すもの)が「酸」であり、プロトン受容体(受け取るもの)が「塩基」です。従ってHClはH+を出しますから「酸」。一方水は場合によっては酸にもなりますし、塩基にもなります。例えばH+と水を混ぜればヒドロニウムイオン「H3O+」になりますから、水は「塩基」としてH+を受け取っていますし、アンモニアと混ぜれば、水のH+をアンモニアにわたしていますので、H+供与体ですから「酸」です。
ブレンステッドの酸塩基、は定義なので、どんな化合物も「H+」を出す可能性さえあれば「酸」になります。CH4だってNH3だってプロトンを出せますので、「酸」として定義可能です。メタンが酸だって!と驚かれるかもしれませんね。そうですね、酸ではないですね。しかし、ここは定義なので「酸」です。むしろ「酸」としての作用は、どれほどたくさん「H+」を出すことができるのかにかかっています。従って、「定義としての酸」と「酸の強さ」は別物なのです。
酸の強さは、そのままH+がどれほどたくさん出るかにかかっています。これは酸塩基平衡の式で考えると良さそうです。一般の水中での酸塩基の平衡式は
HA + H2O –> A- + H3O+
です。酸塩基平衡のKaの式は
Ka = [H3O+][A-]/[HA]
になります(水の濃度の話から、[H2O]を省くって話はいいですね)。従ってKaが大きくなれば、酸として強くなり、Kaが小さくなれば弱酸です。酢酸は水中で約1%(0.1 Mの場合)しか解離していませんから弱酸ですが、このKaは4.76 x 10-5mol/Lです。となると、弱酸の場合(強酸でも同様ですが)、大事なのは指数部分の「-5」なのです。従って見やすくするための対数をとり、−1をかけたものをpKaとして使います。pKaでは数字が大きいほど弱酸です。
酸塩基平衡の平衡は混ぜてできる酸と共役酸(平衡式の右辺にできる酸)のpKaを比較することで議論できます。一般に左辺が強酸なら(pKaが小さい)平衡は右に傾きますし、左辺が弱酸(pKaが大きい)時は、平衡は左辺に傾きます。平衡位置はこれらのpKa智の差の大きさで議論できることになります。
さて、酸の強さは何で決まるのでしょうか。酸「HA」の解離平衡式をもう一度眺めてみましょう。酸「H+」がたくさん出るということは、共役塩基「A-」も同じだけ出てくると言うことです。すなわち、強酸ならば「A-」もたくさんでなければならない。従って「A-」がより発生しやすいように「安定化された」ものは強酸であると言うことになります。どうしたら「A-」の安定化ができるでしょうか。いくつかやり方はありますが、1.電気陰性度(ハロゲンなどのマイナスイオンは安定ですね)、2.結合のs性(アセチレンのアニオンがで安野はこの性であると説明されます)、3.共鳴構造がたくさんあること(アルコールとカルボン酸、フェノールの酸の強さの差)、4.誘起効果などによるマイナス電荷の分散(クロロ酢酸やトリフルオロ酢酸の酸性度の差)があります。いずれも、プロトンを出すことにより生じる「−1」の電荷をどのように分散するかにかかっていると言えるでしょう。従って、酸は共役塩基の安定化によってその強さが決定されるのです。
有機化学における酸塩基の概念について勉強しました。
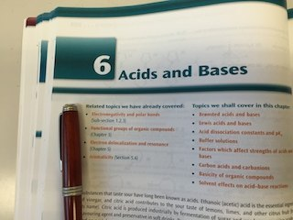
Tuesday, 2 December 2014....
Acids and bases 1